
あなたは繊細で傷つきやすい人ですか?もしかしたらあなたは、人一倍敏感な人「HSP」かもしれません。この診断を受けるとあなたがHSPなのか、そして何型のHSPなのかわかります。自分のタイプと対処法を知って感じている生きづらさを解消しましょう。
HSP(Highly Sensitive Person/ハイリー・センシティブ・パーソン)とは、刺激に対する感受性が生まれつき強い人のことを指します。心理学者エレイン・N・アーロン博士が1990年代に提唱した概念で、人口のおよそ15〜20%に見られるとされています。
HSPの人は、他人の感情や環境の変化に敏感で、音や光、人混みなどの刺激を強く感じやすい傾向があります。一方で、物事を深く考える力や共感性、創造性に優れているという特徴もあります。
これは病気や障害ではなく、「神経系の働き方の個性」として理解されています。自分の特性を知ることで、日常生活や人間関係のストレスを軽減し、より自分らしい生き方を見つけることができるでしょう。
HSPには、「DOES(ダズ)」と呼ばれる4つの特徴があります。これらをすべて満たす人がHSPと呼ばれます。DOESは以下4つの特徴の頭文字から来ています。
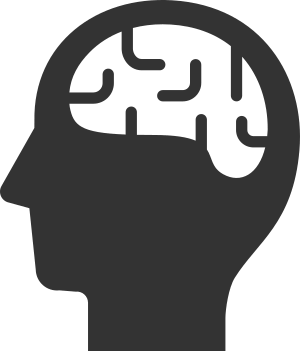
何事も様々な角度からじっくり考えます。慎重に考え抜くため、浅はかな行動や決断で失敗することは稀です。その分、物事を決めるのに時間がかかったり、行動が遅くなったりします。調べ物をするときも、とことん調べます。浅い冗談話よりも、どちらかといえば哲学的な深い話を好みます。

様々な外界からの刺激に反応しやすいのが特徴です。騒々しい人混みや大きな音などにストレスを感じます。ワイワイ友人と過ごす時間を楽しくは思えますが、帰宅後にかなり疲労を感じるなど消耗しやすい体質です。些細なことに傷つきやすく、ちょっとしたことに過剰に驚いてしまう傾向もあります。

誰かが喜んだり悲しんでるのを見ると、感情移入して自分も同じような気分になりやすい傾向にあります。人の機嫌に左右されやすく、怒っている人が近くにいると強いストレスを感じます。他人の感情を察するのが得意で、相手を理解しつつ自分を合わせることができます。周りの人が幸せになっているのを見ると、人一倍嬉しい気持ちになります。

五感の鋭さを持っており、些細なことが気になります。まぶしい光、強い臭い、肌触りの悪い布、ケガしたときの痛み、ちょっとした音などに敏感に反応します。カフェインにも過剰に反応しやすい体質です。相手の外見や声、感情などの小さな変化にも気づけます。自他ともに神経質な人だという自覚があるかもしれません。
当サイトのHSP診断テストは、40問3分の質問に回答することで、あなたのHSPに関することが以下の項目で詳細にわかります。