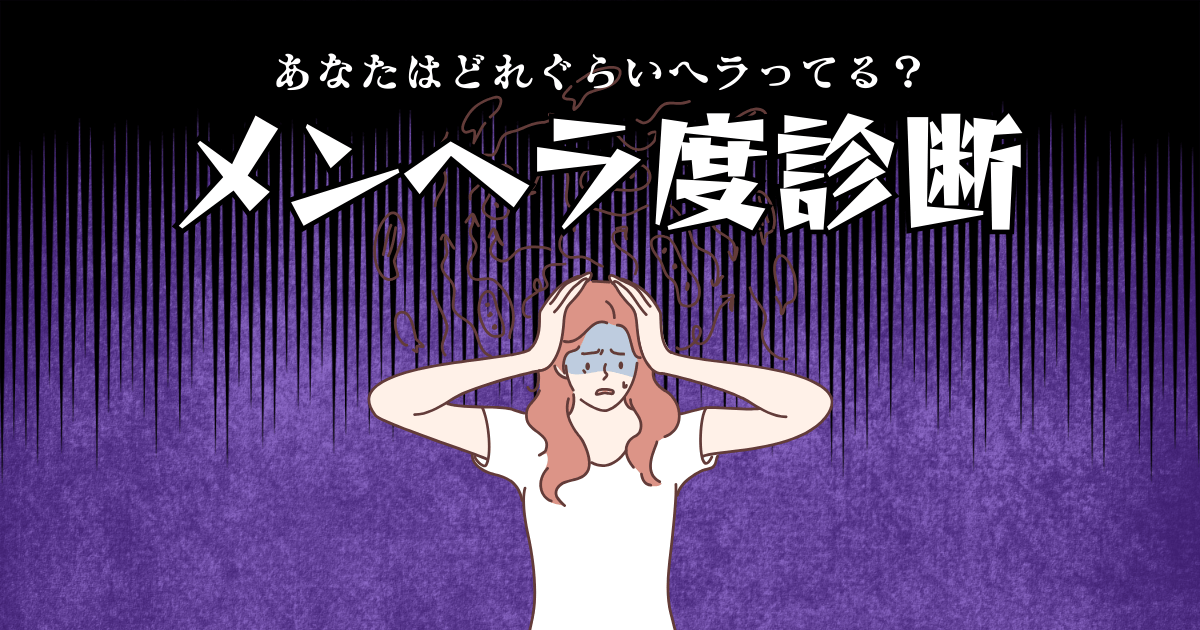
メンヘラとは、メンタルが不安定で精神に問題を抱えた人を指す日本の俗語です。30問の診断ですが、しっかりした結果を知ることができます。男性・女性どちらも当てはまる結果です。この診断では「情緒不安定」「他者依存」「ネガティブ思考」「自己評価の低さ」「感情表現の強さ」の5項目から、あなたのメンヘラ度をチェックします。
「メンヘラ」という言葉は日本のインターネットスラングで、精神的な不安定さや心の問題を抱えた人を指す表現です。
この言葉は、もともと「メンタルヘルス」に由来しており、「気分が不安定」「情緒の浮き沈みが激しい」「対人関係に過度に依存しやすい」「ネガティブで自己否定的な思考」「感情表現が強い」などの特徴を持つ人に使われます。
SNSなどで自分の感情を頻繁に投稿したり、周りからの共感や理解を求める傾向があるともされています。
幼少期のトラウマや愛情不足、繰り返される人間関係の問題、自尊心や自己評価が低いことがメンヘラ傾向を強めるとされています。
近年では「メンヘラ」という言葉が広く使われるようになり、軽い冗談や自分を揶揄する際に用いられたりしますが、偏見の元にもなりやすいため注意が必要です。
単なる個性や性格だけでなく様々な背景やストレス要因が関わっていることも多いため、安易にメンヘラというレッテルを貼らずに状況や背景に理解を持つことが大切です。
情緒不安定さはメンヘラの大きな要因と言われており、気分が急激に変わりやすく、コントロールが難しい状態を指します。たとえば、些細なことに極端に反応したり、突然気分が沈んだり高揚したりします。これはストレスや不安、過去の経験などが影響することが多く、メンヘラ傾向がある人にとって日常的なストレス源となり得ます。情緒不安定さが続くと、他人との関係にも影響を及ぼします。
他者依存は、自分の価値や安心感を他人との関係に強く依存する傾向です。これは孤独を避けたいという欲求から生じ、過度な期待や束縛の要因になることもあります。メンヘラ傾向がある人にとって、他者に依存することで一時的に心の安定を保とうとする一方、相手に依存しすぎることで関係が不安定になるリスクもあります。
ネガティブ思考は、物事を悲観的に捉えてしまう心理状態です。これにより自分や周りに対して否定的な見方が強まり、自己嫌悪や無力感が深まることがあります。ネガティブな考え方が強いと対人関係でも不信感が生まれやすくなり、周囲から孤立しやすいといった悪循環に陥るケースもあります。
自己評価の低さは、自己肯定感が不足している状態で、自分の価値を過小評価しやすくなります。メンヘラ傾向が強い人は、自己評価の低さが対人関係や日常生活に影響を及ぼし、周りの意見や評価に左右されがちです。そのため、他人の期待に応えようと無理をしたり、依存的な行動に結びつくこともあります。
感情表現の強さは、SNSや会話において自分の感情や考えを頻繁に表現する傾向です。これにより他者からの理解や共感を求めることが多く、自分の不安やストレスを緩和しようとします。感情表現が激しいと他者に重いと思われてしまうことも多く、結果的に対人関係にストレスが生じがちです。